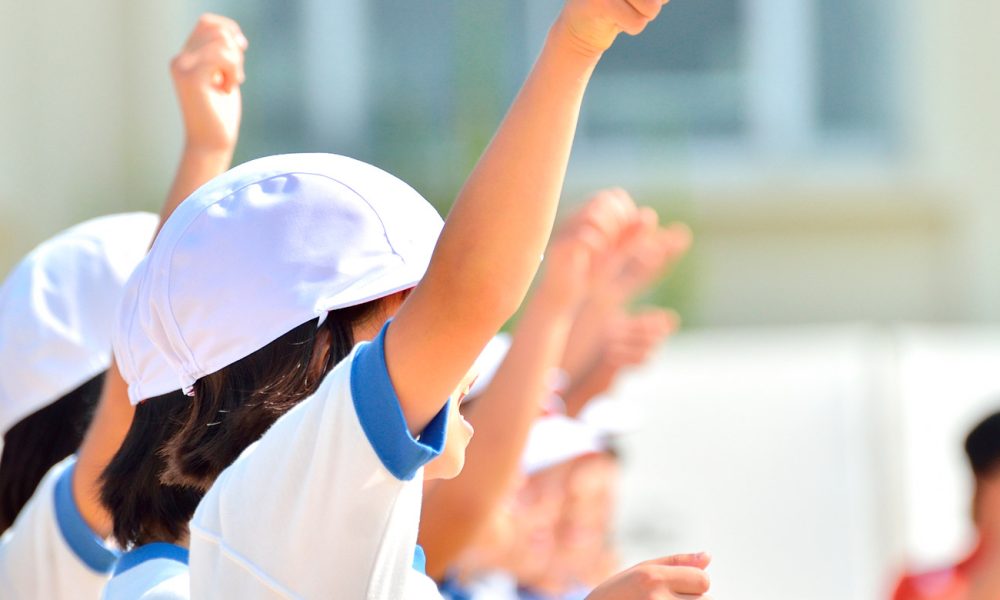
小学生の体育の授業の評価基準。体育の評価はどのように決まっている?
子どもが小学生になると、年に2回通知表を受け取りますよね。そんな通知表は2020年度に評価基準が改正され、これまでと評価方法が変わりました。なかでも、体育の授業は実技が中心のため、どのような基準で評価されているかわかりにくいという方も多いのではないでしょうか。今回は、小学校の体育の授業の評価基準について解説します。体育の評価を上げるためにできることも合わせて紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
日本テレビ運営のドリームコーチングは、良質なスポーツ体験を提供するサービスです。
アスリートやプロのコーチから個別で指導が受けられます。
プロのトレーニングを受けてみたい方は、ぜひドリームコーチングの利用を検討してみてください!
目次
小学校の通知表の評価基準が2020年度から改定された
小学校の通知表の評価基準は2020年度に改定されました。ここではまず、小学校の通知表の評価基準について解説します。
評価基準は3つの観点
これまで小学校の通知表は4つの観点から評価を行っていました。
- 意欲・関心・態度
- 思考・判断・表現
- 技能
- 知識・理解
これら4つの観点から、各教科ごとに学校で評価基準を決めて評価がされていました。
しかし、2020年度の改定により、評価が3つの観点に変更されています。
- 知識・技能(知識やスキルが充分に身についたかどうか)
- 思考・判断・表現(課題を見つけて解決する力や思いを表現できているか)
- 主体的に学習に取り組む態度(意欲や積極性があるか)
これまでは、学習に対して興味をもって取り組むことができるかという「意欲・関心」を重視する評価方法でしたが、改定後は、知識を身につけ、さまざまな知識と関連させながらさらに深く理解し、学んだことを社会で生かそうとする能力を育成することが重要視されるようになりました。
参考:<政府広報オンライン 2020年度、子供の学びが進化します!新しい学習指導要領、スタート!
評価方法は「絶対評価」が基本
通知表の評価方法は、かつては「相対評価」で行われていました。相対評価とは、クラス全体の中で、どの順位に位置するかを示す評価方法です。相対評価の場合、テストの点数は同じでも、全体の成績が良いクラスと、悪いクラスの場合では、評価に差が出てしまいます。
しかし、現在では通知表の評価方法は「絶対評価」が基本とされています。絶対評価とは「その子ども自身がどれくらい伸びたか」を評価する方法です。
ほかの子どもと優劣をつける評価ではなく、子ども自身が教科における目標をどれくらい達成できたかに重点を置いて評価を行います。
ただ、主体的に学習に取り組む態度については、どうしても教師の主観的な評価になってしまう部分があります。発言の回数やノートの取り方など、形式的な評価ではなく、子どもたちが自ら目標をもって、自分の頭で考え・表現し、知識を身につけることができているかという、子どもの意思を評価する必要がある点が重要です。
小学校の体育の評価基準とは?

体育は実技が中心であるため、どのように評価されているのかわかりにくいと感じることも多いのではないでしょうか。ここでは、小学校の体育の評価基準について解説します。
3つの観点に沿って内容ごとに評価
体育においても、「知識・技能」「思考・判断力・表現力」「主体的に学習に取り組む態度」の3つの観点から、それぞれの内容のまとまりごとに評価規準が作成されます。
小学校の体育の内容のまとまりは下記のようになっています。
| 第1学年及び第2学年 |
|---|
| A.体つくりの運動遊び |
| B.器械・器具を使っての運動遊び |
| C.走・跳の運動遊び |
| D.水遊び |
| E.ゲーム |
| F.表現リズム遊び |
| 第3学年及び第4学年 |
|---|
| A.体つくり運動 |
| B.器械運動 |
| C.走・跳の運動 |
| D.水泳運動 |
| E.ゲーム |
| F.表現運動 |
| G.保健(1)健康な生活/td> |
| G.保健(2)体の発育・発達 |
| 第5学年及び第6学年 |
|---|
| A.体つくり運動 |
| B.器械運動 |
| C.陸上運動 |
| D.水泳運動 |
| E.ボール運動 |
| F.表現運動 |
| G.保健(1)心の健康 |
| G.保健(2)けがの防止 |
| G.保健(3)病気の予防 |
出典:文部科学省国立教育政策研究所 「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料
例えば「器械・器具を使っての運動遊び」という内容においては、3つの観点から下記のような評価規準が作成されます。
| マット運動では、マットを使った運動遊びの行い方を理解することができたか(知識・技能) |
| マット運動で色々な方向に回転したり、手を使って体を支えることができるかどうか(知識・技能) |
| 鉄棒では、ぶら下がりや簡単な回転ができるかどうか(知識・技能) |
| 跳び箱では、跳び乗りや跳び下り、手をついてまたいだりすることができるかどうか(知識・技能) |
| 遊び方を工夫しているか、考えたことを友達に伝えることができているか(思考・判断・表現) |
| 進んで運動遊びに取り組もうとしているか、順番や決まりを守れているか、場の安全に気を付けたりすることができるか(主体的に学習に取り組む態度) |
参考:文部科学省国立教育政策研究所 「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料
このように、3つの観点からそれぞれ評価規準が作成され、評価が行われます。
ただし、実技の授業に参加できなかった場合は「評価しない」という判断になります。子ども自身の成長を評価する絶対評価であるため、評価がつかなくても周りの子どもと比べる必要はありません。
技能だけでなく、参加姿勢や意欲も大切
体育の学習評価においても、技能だけでなく参加する姿勢や意欲も大切な評価項目となります。
文部科学省発行の小学校学習指導要領によると、体育の授業は、基本的な動きや技能を身につけるだけではなく、生活するうえで健康や安全への理解を深めること、運動や健康において自分自身で課題を見つけること、運動に親しむことで健康維持や体力向上を目指すことなどを目標としています。
体育の授業を通して運動の楽しみや喜びを感じることで、体の健康はもちろん、心の健康にも深く関係することを実感して、生涯において楽しくスポーツを続ける基盤を作ることが一番大切なポイントです。
小学校の体育の評価を上げるためにできること

技能だけでなく、さまざまな目的から評価が行われている小学校の体育ですが、評価を上げるためにはどんなことができるのでしょうか?体育の評価を上げるためにできること3つを紹介します。
①家庭で一緒に運動を楽しむ
まずは、運動に対する子どもの意欲を高めることがポイントです。子どもが運動に興味を持ち、楽しく取り組めるよう、家庭でも親子で一緒に運動する習慣をつくってみましょう。子どもが興味のあるスポーツを一緒に楽しんだり、スポーツ観戦に行ったりするのもおすすめです。
➁上達できる方法を親子で考える
体育の授業では、運動に取り組む姿勢も評価につながります。まずは家庭で、子どもが意欲的に運動に取り組むことができるよう促してみましょう。
例えば、運動が上手な人を観察して、親子で一緒に上達方法を研究することで、運動に対する意欲が高まります。体育の授業においても、どうやったら上達できるのか、自分なりに思考しながら取り組む姿勢は、「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」の評価につながるでしょう。
③苦手な運動は個人レッスンを受けてみる
運動への意欲を高めるためには、スポーツの個人レッスンを受けてみることもおすすめです。家庭でなかなか運動に取り組む機会がない場合や、運動にどうしても苦手意識があるお子さんの場合は、まず小さな達成感を味わうことからはじめてみましょう。
個人レッスンでは、子どものペースや苦手に合わせて指導してもらえるため、成長スピードも速く、技能を身につけることで自信がつけば、さらに体育の授業にも積極的に参加できるようになるでしょう。
関連記事:運動神経のいい子がしている習い事!体操の個人レッスンが人気!
小学校の体育の評価アップには、まずは意欲を高めることが大切
小学校の体育の評価は、「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」の3つの観点から評価が行われており、技能だけでなく自分で考えて取り組む姿勢や、スポーツに対する興味も大きなポイントです。
体育の評価を上げるには、まず子どもが運動に興味を持てるよう、家庭でも一緒に運動に取り組むことがおすすめです。また、スポーツの個人レッスンを受けることで、子どものペースに合わせて技能を身につけることができるため、さらに運動への意欲を高めることができるでしょう。
日本テレビ運営のドリームコーチングは、アスリートやプロのコーチから個別のスポーツ指導を受けられるサービスです。
ドリームコーチングなら、お子さんのレベルに合わせて気になる種目を一から学べます。
夏休みや冬休みなどの長期休暇でのご利用も、単発でのご利用もOK!スポーツの個別指導ドリームコーチングを検討してみてください。



 ツイート
ツイート
 シェア
シェア
 送る
送る







